◎ 延納 ・ 物納の許可限度額の計算
物納申請税額 (物納許可限度額) の計算方法は?・・・・・
物納申請書の別紙 『金銭納付を困難とする理由書』 に金額等を記入して計算します
| ◆ 延納することができる金額 (延納許可限度額) の計算方法 |
容易に換金できる財産は、全て期限内現金納付に充てることが求められます
| ① 納付すべき相続税額 | |
| 現 金 納 付 額 | ② 納期限において有する相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産 (現金、預貯金その他の換価が容易な財産(上場株式等)の価額に相当する金額) |
|---|---|
| ③ 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費 | |
| ④ 申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
| ⑤ 納期限に金銭で納付することが可能な金額 ( 「現金納付額」 という) (②-③-④) | |
| ⑥ 延納許可限度額 (①-⑤) | |
延納を継続することが困難となった場合には、その納付を困難とする金額を限度として、
相続税の申告期限から10年以内の申請により、延納から物納に変更することができる
| ◆ 物納することができる金額 (物納許可限度額) の計算方法 |
(近い将来確実に入る納税者自身の収入等を含む) を控除した金額
| ① 納付すべき相続税額 | |
| ② 現金納付額 (上記の延納の⑤) | |
| 延 納 に よ り 納 付 で き る 金 額 | ③ 年間の収入見込額 |
|---|---|
| ④ 申請者 及び 生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 | |
| ⑤ 申請者の事業の継続のために必要な運転資金 (経費等) の額 | |
| ⑥ 年間の納付資力 (③-④-⑤) | |
| ⑦ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 | |
| ⑧ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 | |
| ⑨ 上記1の③ 及び ④ | |
| ⑩ 延納によって納付することができる金額 { ⑥ × 最長延納年数 + (⑦-⑧+⑨) } | |
| ⑪ 物納許可限度額 (①-②-⑩) | |
物納申請を自ら取り下げて、物納から延納へ変更を行うことはできません
『金銭納付を困難とする理由書』 には、計算の根拠となった資料等の写しを添付します。
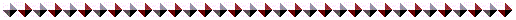
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/