◎ 事実婚 と 法律婚
(税制 と 年金制度)
<事実婚> の場合の税制 及び 社会保障制度の取扱い
| ◆ 現行の婚姻制度・・・・氏 (姓) の問題を含め |
| ● 法律婚主義 ・・・・ 届出婚を採用 |
| 民 法 (739条) | 婚姻は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによって、 その効力を生ずる |
| ● 夫婦同氏の原則 ・・・・ 夫又は妻のいずれかの氏 (姓) を選択 |
| 民 法 (750条) | 婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は 妻の氏を称する |
| (ⅰ) 事実婚を選択するか? 若しくは (ⅱ) 婚姻届を提出し、旧氏(姓) を通称として使用する |
| ◆ 事実婚に厳しい税制 |
主として徴税の便宜から、画一的な規定をし法律婚主義を採っています
| 所得税 | 配偶者控除(所法83条) | 婚姻の届出をした者 |
|---|---|---|
| 扶養控除 (所法84条) | 民法上の親族で、一定の基準日の現況で判断 | |
| 相続税 | 配偶者に対する相続税の税額軽減 (相法19条の2) | |
| 贈与税 | 贈与税の配偶者控除 (措法21条の6) | |
| ◆ 事実婚にも優しい社会保険制度 |
| 健康保険法 (第3条⑦) | 被扶養者とは、被保険者の直系尊属、配偶者 (届出をしていな いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫 及 び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持する者 |
| 厚生年金保険法 (第5条⑧) | 配偶者 (夫 及び 妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上 婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする) |
| ○ 事実婚の夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者になれ |
| ○ 夫が亡くなったときは、妻として遺族基礎年金や遺族厚生年金も受け取れます |
| ○ 離婚時の年金分割も可能です |
(生計維持関係) を証明する書類が必要です
| 内 容 | 事実婚 | 法律婚 | |
|---|---|---|---|
| 年 金 制 度 | 配偶者として第3号被保険者になれる | ○ | ○ |
| 夫の遺族年金を受けられる | ○ | ○ | |
| 税 制 ・ 相 続 | 所得税の配偶者控除を受けられる | × | ○ |
| 相続税の配偶者の非課税枠を利用できる | × | ○ | |
| 配偶者として相続人になれる | × | ○ | |
日本の税制は、事実婚に対しては厳しい法規定となっており、結婚観の変化 ・
女性の社会進出に伴うライフスタイルの多様化に税制も対応していかなければと思います。
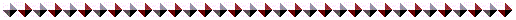
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/